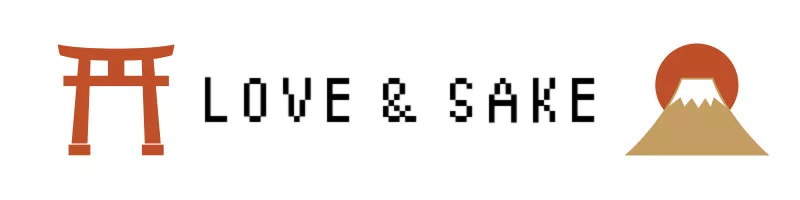圖片來源:日本國家旅遊局
繼上次聊完洗米之後,這篇來簡單說明一下蒸米這件事。
在清酒的釀酒分工中,我們知道有首席釀酒師(釀造總責任者)又稱杜氏,旗下指揮著負責製麴的「麴師(屋)」、「酒母師(酛屋)」,以及指揮著其他工作人員的「頭」。而除了這三位助手外,另外還有負責蒸米的「蒸米師(釜屋)」以及負責壓榨上槽的壓榨師「船頭」」。可見蒸米在釀酒工作中的重要性。
「蒸米師」(釜屋)負責將浸泡後的米粒經蒸汽加熱至理想狀態,它會直接影響麴師製麴效率與酒母師發酵時的酵母活性。若前置蒸米工序出現偏差,後續麴品質與發酵穩定性皆會受到很大的影響;因此到酒造參訪時,仔細觀察蒸米設備與作業手法,也能大致了解酒造的核心技術水準。
蒸米的機制與原理
清酒原料的蒸米,並不是以炊煮的方式處理,而是利用蒸汽來蒸煮,目的是使麴菌與酵母更容易發揮作用。蒸米的首要目的是將米中的澱粉糊化(α化/Gelatinization),由於生米澱粉顆粒呈高度結晶結構,需經過吸水(含水率約 30–40 %)與加熱(60–80 °C)才能達到糊化臨界點,使澱粉從結晶態轉為非晶膠糊態,供麴菌與酵素分解。
而糊化需達到「完全糊化」卻不能失去外表的硬度與立體感,以免影響麴菌孢子附著與生長,也就是所謂的 粒立性(Saba-kei),指的是指蒸後米粒的分離度,與蒸汽分布均勻度相關,可通過分批注入(抜け掛け法)或布料分散蒸汽來提升,同時降低後續製麴結塊風險。
另外,蒸汽注入提昇溫度時會影響蛋白質。米中主要蛋白質為穀蛋白(glutelin)及醇溶蛋白(prolamin),加熱過程中蛋白質部分變性,會讓蛋白質結構鬆散化,來促進麴菌分泌蛋白質酶將其水解成胺基酸,可增加酒中的旨味,但過度變性反而可能降低可溶性胺基酸濃度,導致酒質偏淡,這個時候就需要透過蒸汽溫度與時間精密調控。
此外,蒸汽加熱還具有殺菌效果,能殺死附著於米上的野生酵母與雜菌,避免污染酒母與酒醪階段,穩定發酵過程。不過要注意到若蒸汽分布不均,仍可能有殘存雜菌,故傳統甑內常鋪設麻布或在甑壁與米之間置木片分散蒸汽。

圖片來源:日本國家旅遊局
蒸米時所用的蒸汽分類
(一)濕蒸汽:接近飽和溫度,含有水滴或水霧,易在甑內壁產生水滴,導致部分米過度加熱(「甑肌」)或蒸氣分布不均。
(二)乾蒸汽:接近飽和溫度,但不含水滴,能均勻傳遞熱能,有助形成理想的「外硬內軟」蒸米。
(三)過熱蒸汽(強蒸汽):超過飽和點溫度,為高溫乾燥蒸汽,含較高熱量,可在短時間內製成硬蒸米,若使用過度則可能造成米裂(釜割れ)。

圖片中可見大量霧狀蒸氣從甑冒出,濕度高且帶有水滴,常見於蒸氣剛注入、尚未完全均勻散布時(可能導致甑壁水珠與蒸氣分佈不均)。
圖片來源:japan up close
蒸米設備來說,目前主流上有傳統的「甑」與近代的連續蒸米機
甑(こしき)是一種底部開孔的桶狀蒸器,常見材質為杉木或金屬,加熱來源為鍋爐或瓦斯爐。使用甑時需避免蒸氣集中導致一部分米過濕。通常會在甑底放置木片,再鋪上麻布或耐熱布以擴散蒸氣並避免甑肌的產生。現在也有為了防止甑肌現象而在甑壁上做了兩層斷熱的吟釀甑。
連續蒸米機則是以輸送帶或縱向滾筒形式將浸漬米放於輸送帶上,以蒸氣自下方加熱,優點是可大量穩定蒸
米,但也較為昂貴,參訪酒造時如果有看到連續蒸米機,在酒造允許下,不妨拍照紀錄。
在輔助設備上則常見酒造會增添一台具有加壓強蒸的「整蒸機」來調整蒸汽溫度與蒸汽的乾濕度。
圖片來源:Nagata
在蒸米的操作流程與步驟
(一)浸泡時間與含水量測試:依米品種、精米步合與水溫做調整,長可達1-2小時,短則約數十秒至數分鐘。浸泡後會取樣以千克度比重計估算含水率,確保達標後再進行排水與靜置瀝乾。
(二)蒸時與溫度控制:前半段蒸時約40~60分鐘,依甑型與蒸米量而異;後半段調溫的最後 10–15 分鐘則調至 102–103 °C 的高溫乾蒸汽,確保內部完全糊化與蛋白質適度變性。
(三)蒸後冷卻:蒸後快速降至約 50–60 °C,再攤開於木桶或竹簀上散熱,以避免過熱效應;散熱過程則要注意到空氣流通,防止表面回生(retrogradation)或過乾。
蒸米成效常用的檢測方法
(一)剖開目視法:隨機取樣 10–20 粒米剖開,觀察白芯(未糊化)比例與內外糊化均勻度,常用光學顯微鏡輔助判讀。
(二)差示掃描量熱法(DSC):利用 DSC 測量糊化過程中吸熱峰與放熱峰溫度、焓變化(ΔH),進而量化糊化溫度範圍與均勻性,為優化蒸米參數提供科學依據。
蒸米常出現的問題與解決方法
如果是「過硬蒸米」,一般會繼續延長蒸米時間或是提高溫度。但相反地,如果在洗米與浸漬時過久,則會造成過軟蒸米(通常過軟蒸米問題較大,不妨可以問問酒造有沒有出現過這個現象以及該如何解決等)。
除了過硬或過軟外,還會發生「未熟蒸(生蒸)」現象,也就是米心仍白濁,這表示蒸氣未充分滲入,如果蒸時沒有問題,就要注意蒸氣分佈的問題。另外如果發現蒸氣在甑壁凝結成水滴,讓靠壁之米局部過濕或過熱,這個稱為「甑肌」,就必須要在甑壁與米之間放布料或是改用具有斷熱設備的吟釀甑。
結語
不管是上一篇提到的洗米或是這篇提到的蒸米,都是屬於原料處理階段的工序,原料處理如果無法達到釀酒設計的理想狀態,對後續製麴以及酒母會有相當大的影響。這也難怪有人會戲稱釀酒不是「一麹、二酛、三造り」,而是「一に蒸し、二に蒸し、三に蒸し」。下次如果有機會到酒造參訪,別忘了多在蒸米區停留一會,看看這家酒造的「釜屋」功力。
參考資料:
1.椎木 敏, 清酒もろみにおけるα-アミラーゼの吸着と蒸米の溶解, 日本釀造協會誌, 第79卷第12期。
2.上田 護國, 蒸米の吸水率を制御指針とする製麹技術の開発とその応用例, 日本釀造協會誌, 第115卷第2期。
3.公益財団法人日本醸造協会編「増補改訂清酒製造技術新版」(日本醸造協会, 2009)
4.公益財団法人日本醸造協会編「最新酒造講本」(日本醸造協会, 2007)
5.公益財団法人日本醸造協会編「酒造教本」(日本醸造協会, 2009)
日文版原文
◆酒蔵見学心得シリーズ◆
■前言
前回「洗米」についてお話しした後、本稿では「蒸米」について簡単にご説明します。
日本酒の醸造分担においては、まず杜氏(醸造総責任者)が指揮を執ります。杜氏の下には、麹を仕込む麹師(麹屋)と酒母を仕込む酒母師(酛屋)、そして他の職人を取りまとめる「頭」がいます。さらにそのほかに、浸漬した米を蒸す蒸米師(釜屋)と、搾りおよび上槽を担当する「船頭」が配置されます。これにより、蒸米が醸造工程の中でいかに重要かがわかります。
蒸米師(釜屋)は、浸漬後の米粒を蒸気で理想的な状態に加熱する役割を担い、その出来栄えは麹師の製麹効率や酒母師の酵母活性に大きく影響します。前工程で蒸米にずれが生じると、以降の麹品質や発酵の安定性にも深刻な影響が及ぶため、酒蔵見学の際には蒸米設備や作業方法をじっくり観察することで、その蔵の技術力を把握できます。
◎酒蔵見学シリーズ(二)生米を蒸してご飯に?|蒸米について語る
●蒸米のメカニズムと原理
清酒の原料である米は、炊飯とは異なり蒸気で蒸すことで処理します。その目的は、麹菌や酵母が活動しやすいようにすることです。蒸米の第一目的は、米中のデンプンを糊化(α化/Gelatinization)させることにあります。生米のデンプン粒は高度に結晶化しているため、含水率約30~40%まで吸水し、さらに60~80℃で加熱することで糊化臨界点に達し、結晶状態から非晶質のゲル状へ転移し、麹菌や酵素に分解されやすくなります。
糊化は「完全糊化」を達成しながら、外観の硬さや立体感を失わないことが必要です。これにより麹菌の胞子付着や生育が妨げられず、「粒立ち」(Saba-kei)と呼ばれる蒸後の米粒の分離性を保ちます。粒立ちは蒸気の分布均一性に関係し、分批投入(抜け掛け法)や布などを用いた蒸気拡散で向上させることで、後続の製麹時の結塊リスクを低減できます。
また、蒸気注入による加熱は蛋白質にも影響を及ぼします。米中の主要な蛋白質はグルテリン(glutelin)やプロラミン(prolamin)で、加熱過程で部分的に変性し、構造がゆるむことで麹菌が分泌する蛋白質分解酵素によりアミノ酸へと分解され、旨味を増加させます。しかし、変性が過度になると可溶性アミノ酸濃度が低下し、酒質が淡泊になるため、蒸気温度と時間を精密に制御する必要があります。
さらに、蒸気加熱には殺菌効果もあります。米表面に付着した野生酵母や雑菌を殺滅し、酒母や醪の段階での汚染を防ぎ、発酵を安定させます。ただし、蒸気の分布が不均一だと雑菌が残存する可能性があるため、伝統的な甑の内部には麻布を敷いたり、甑の壁と米の間に木片を挟んで蒸気を拡散させたりします。
●蒸米に用いる蒸気の分類
(一)湿蒸気:飽和に近い温度で水滴や水霧を含みやすく、甑の内壁に水滴が生じると一部の米が過加熱(甑肌)されたり、蒸気が不均一に分布したりします。
(二)乾蒸気:飽和に近い温度ながら水滴を含まないため、熱エネルギーが均一に伝わり、理想的な「外硬内軟」の蒸米を形成しやすいです。
(三)過熱蒸気(強蒸気):飽和温度を超えた高温乾燥蒸気で、熱エネルギーが大きく、短時間で硬い蒸米を作れますが、使い過ぎると米粒が割れる(釜割れ)可能性があります。
●蒸米設備
現在主流なのは伝統的な「甑」と近代的な連続蒸米機です。
甑(こしき)は底部に孔を持つ桶状の蒸し器で、材質は杉木や金属が一般的です。蒸気の熱源はボイラーやガス釜などを用います。甑使用時は蒸気が一部に集中して米が過度に湿るのを防ぐ必要があり、甑底に木片を敷き、その上に麻布や耐熱布を重ねて蒸気を拡散させ、甑肌の発生を防ぎます。近年は甑壁に二重断熱構造を持たせ、甑肌を防止した吟醸甑も登場しています。
連続蒸米機は、浸漬米を輸送ベルトや縦型ローラーに載せ、下方から蒸気を当てて加熱する仕組みです。大量かつ安定した蒸米が可能ですが、設備費用が高額です。酒蔵見学で連続蒸米機を見かけた際は、許可を得て写真記録するとよいでしょう。
また、補助設備として加圧強蒸型の「整蒸機」を導入し、蒸気の温度や乾湿度を調整する蔵もあります。
●蒸米の操作手順とパラメータ
(一)浸漬時間と含水率測定:米の品種、精米歩合、水温に応じて調整し、最長で1~2時間、最短で数十秒から数分行います。浸漬後は検体を取り、比重計で含水率を測定して基準を満たしていることを確認し、その後排水・静置して余分な水分を切ります。
(二)蒸時と温度管理:前半は甑の種類や蒸米量に応じて約40~60分蒸し、後半の最後10~15分は102~103℃の高温乾蒸気に切り替え、米心の完全糊化と蛋白質の適度な変性を確保します。
(三)蒸後冷却:蒸し終えたら速やかに50~60℃まで温度を下げ、木桶や竹簀の上に広げて放冷します。過熱の余勢を避けるためであり、放冷時には空気循環を確保し、表面の回生(retrogradation)や乾燥過多を防ぎます。
●蒸米の効果検査方法
(一)剖開目視法:ランダムに10~20粒の米を剖開し、白芯(未糊化)部分の割合や内外の糊化均一性を観察します。必要に応じて光学顕微鏡で補助観察を行います。
(二)差示走査熱量測定(DSC):DSCを用いて糊化過程の吸熱ピーク・放熱ピークの温度およびエンタルピー変化(ΔH)を測定し、糊化温度域や均一性を定量化して蒸米パラメータ最適化の科学的根拠を得ます。
●蒸米の主な課題と対策
(一)過硬蒸米:糊化不足または温度低下が原因。蒸し時間を延長するか、後半段階の蒸気温度を上げます。
(二)過軟蒸米:浸漬時間過長や含水率過多が原因。浸漬時間を短縮し、含水率を調整します。
(三)未熟蒸(生蒸):米心が白濁したまま。蒸気浸透不足が原因のため、蒸気分布を見直すか、乾蒸気や分批投入法を検討します。
(四)甑肌:甑内壁で蒸気が凝結し、壁際の米が局所的に過湿・過熱になる現象。甑壁と米の間に布を入れるか、吟醸甑を導入するかなど二重断熱甑や乾蒸気に切り替えます。
●結語
前回の「洗米」に続き、本稿では「蒸米」という原料処理工程を詳述しました。原料処理が設計通りに行われないと、以降の製麹や酒母工程に大きな影響が及びます。そのため、日本酒造りは「一に蒸し、二に蒸し、三に蒸し」とも称されます。次回酒蔵見学の際は、ぜひ蒸米エリアに立ち寄り、釜屋の技術をご覧ください。
參考資料:
1.椎木 敏, 清酒もろみにおけるα-アミラーゼの吸着と蒸米の溶解, 日本釀造協會誌, 第79卷第12期。
2.上田 護國, 蒸米の吸水率を制御指針とする製麹技術の開発とその応用例, 日本釀造協會誌, 第115卷第2期。
3.公益財団法人日本醸造協会編「増補改訂清酒製造技術新版」(日本醸造協会, 2009)
4.公益財団法人日本醸造協会編「最新酒造講本」(日本醸造協会, 2007)
5.公益財団法人日本醸造協会編「酒造教本」(日本醸造協会, 2009)
責任編輯:潘昱嘉
核稿編輯:陳慧