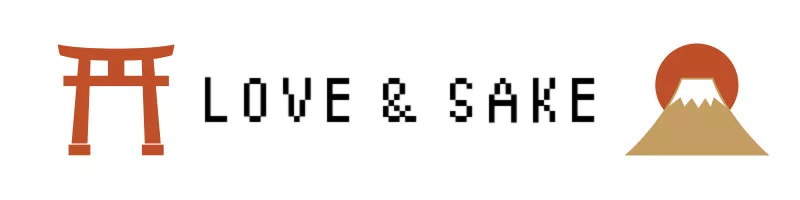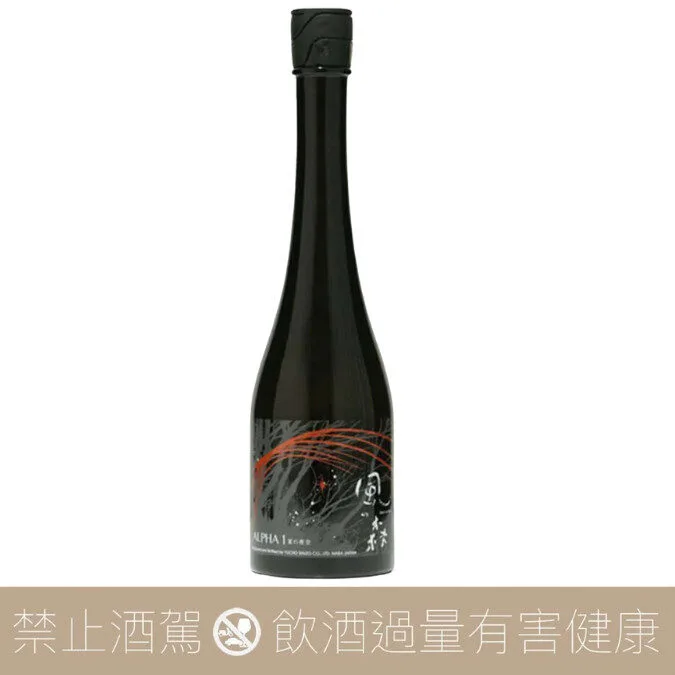圖片來源:OSA官方IG
如果是長期閱讀我文章的讀者應該不陌生,現今大部分的清酒賽事,除了日本官方鑑評會(包含全國新酒鑑評會、地方國稅局及各縣品評會)以20 ℃、日本燗酒大賽以45 ℃與55 ℃之外,絕大部分比賽係以10〜15 ℃作為評審酒溫。
但你是否遇過在日料店、居酒屋、Sake Bar中點清酒,服務人員從冰箱(3〜5 ℃)取出後直接倒入杯中,而你馬上入口後,卻感受不到侍酒師所提到的香氣與口感?甚至會有一股淡淡的苦味?甚者,還會有餐廳拿個冰桶,在旁邊讓酒冰鎮,使你從頭到尾都將酒溫維持在5〜10 ℃之間。
品飲溫度的重要性
事實上,在清酒的世界裡,品飲溫度是一個經常被提及的重點,卻在品飲現場被容易被忽略的細節。
許多人習慣把酒冰到接近啤酒的低溫,或是把燗酒加熱到冒煙才覺得專業。事實上,這些做法往往會犧牲清酒本身的香氣與風味層次。根據日本酒造組合中央會以及與島津善美等學者的研究,如果是屬於香氣跟口感都較低的清爽類酒款才適合在5 ℃、而具有香氣以及有機酸的吟釀酒款則建議以10〜15 ℃,燗酒則不超過 45 ℃,是能讓大多數清酒能展現最佳狀態的溫度帶。

品飲時溫度是關鍵
油長酒造 風之森 ALPHA1 夏之夜空 菩提酛 無濾過生原酒
微微的炭酸氣泡感,帶有微甜的洋梨香氣
為什麼是 10 ~15℃?
根據島津善美等的研究,10 〜15℃飲用可抑制過多的甘味與酒精感,增強較多的檸檬酸與蘋果酸口感,增加清爽度,讓香氣、酸味與旨味達到平衡,特別適合果香明顯的吟釀酒。然而,如果溫度過低(如 5 ℃ 以下),香氣分子揮發受阻,酒香不易釋放,口感也會變得單薄,特別是酸味與苦味反而容易被凸顯。

圖片來源:OSA官方IG
為什麼不要超過 45 ℃?
45 ℃屬於日本酒溫度分類中的「上燗」(じょうかん)。在這個溫度下,旨味和甜味會被放大,酸味與苦味則趨於柔和,酒體變得圓潤而順口。相比之下,若加熱至 50 ℃以上(熱燗),酒精揮發速度將加快,香氣會變得尖銳甚至刺鼻。
溫度所帶來的香氣與口感變化是清酒相較於其他釀造酒類非常特殊的一點,我這次在OSA評審的過程中也發現,有些爭議性酒款(指分數高低差在同一組中非常明顯),在經過稍微升溫後的複評中,竟然達到了一致的共識。
風之森 ALPHA 5 燗之探求 菩提酛 無濾過生原酒 貴釀酒以10年的古酒代替釀造用水、特別為熱燗飲用而推出的「貴釀酒」酒款。
下次從冰箱拿出清酒時,或許在第一口先別急著下定論,隨著逐漸升溫,也試著體會日本酒獨特的溫度魅力吧!
責任編輯:潘昱嘉
核稿編輯:陳慧
參考文獻
1.日本酒造組合中央会, 日本酒のおいしい飲み方
2.清酒に含まれる有機酸の酸味と飲用温度の関係, 島津善美等, 日本釀造協會(2011)
日文版原文
OSA審査日誌 番外編
「日本酒のベスト温度、知ってる?」
日本酒好きなら、一度はこんな経験ありませんか?
お店で日本酒を頼んだら、キンキンに冷えた冷蔵庫(3〜5℃)から出して、そのままグラスへ。…でも、香りが全然立たない!
しかも、なんだか苦味まで感じる…。
さらにお店によっては、ワインクーラーみたいな氷水のバケツにドボン。
最後の一滴まで5〜10℃のまま。
これ、ちょっともったいないんです。
長く私の文章を読んでくださっている方にはおなじみかもしれませんが、現在ほとんどの日本酒コンペティションでは、日本の公式鑑評会(全国新酒鑑評会、地方国税局および各県の品評会を含む)が 20℃、日本燗酒コンテストでは 45℃ と 55℃、それ以外の大半の国際大会では 10〜15℃ を審査温度として採用しています。
実は、日本酒の世界では「飲用温度」はしばしば話題に上る重要な要素でありながら、現場の提供時には意外と見落とされやすい細部なのです。
多くの人は、日本酒をビールのように極端に冷やすか、あるいは燗酒を湯気が立ち上るほど熱くすることを「本格的」だと考えがちです。しかし、これらの方法はしばしば日本酒本来の香りや味わいの層を犠牲にします。日本酒造組合中央会や島津善美らの研究によれば、香りや味わいが控えめな淡麗系の酒は 5℃、香りと有機酸をしっかり持つ吟醸酒は 10〜15℃、燗酒は 45℃ を超えないことが、多くの日本酒が最良の状態を発揮する温度帯とされています。
なぜ 10〜15℃ なのか?
島津善美らの研究によれば、10〜15℃で飲用すると過剰な甘味やアルコール感が抑えられ、クエン酸やリンゴ酸の風味が際立ち、爽快感が増します。これにより香り・酸味・旨味のバランスが整い、特に果実香豊かな吟醸酒に適しています。
逆に5℃以下では、香り分子の揮発が妨げられ、香りが立ちにくくなり、口当たりが薄く感じられます。特に酸味や苦味が強調されやすく、バランスが崩れやすくなります。
なぜ 45℃ を超えないのか?
45℃は日本酒の温度呼称における「上燗(じょうかん)」にあたります。この温度では旨味と甘味が引き立ち、酸味や苦味は和らぎ、酒質はまろやかで滑らかになります。
一方、50℃以上(熱燗)にするとアルコールの揮発が急速に進み、香りが鋭く、時には刺々しく感じられることもあります。
温度がもたらす香味変化の魅力
温度による香りや味わいの変化は、日本酒が他の醸造酒類と比べて非常にユニークな特徴のひとつです。今回のOSA審査の過程でも、評価が大きく割れた(同じ組で得点差が非常に大きい)議論の的となった酒が、再審査で少し温度を上げただけで、全員の評価が一致するという場面がありました。
次に冷蔵庫から日本酒を取り出すとき、最初の一口で慌てて結論を出さずに、温度が少しずつ上がる中で香りや味わいの変化を感じてみてください。それこそが日本酒ならではの「温度の魔法」なのです。
参考文献
1. 日本酒造組合中央会, 日本酒のおいしい飲み方, https://japansake.or.jp/sake/enjoy-sake/how-to-drink-sake/
2. 島津善美ほか (2011) 清酒に含まれる有機酸の酸味と飲用温度の関係, 日本醸造協会誌