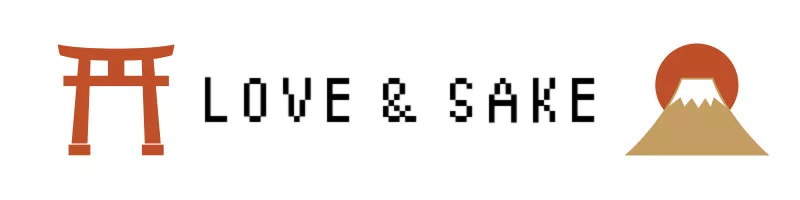燒酎是一門深奧的學問。
今天帶大家了解燒酎的歷史及相關知識,同時探討燒酎的未來發展。
趁著五一連假把鮫島吉廣老師「燒酎履歷書」大作拜讀完畢,將心得跟自己這幾年對燒酎觀察與理解摘要如下,希望能幫助有興趣的朋友初窺一二。
「燒酎」的歷史|源自「泡盛」
燒酎是一種日本傳統蒸餾酒,而現存最古老的日本燒酎可追溯至15世紀琉球王朝的「泡盛」。在江戶時代,泡盛作為薩摩藩獻給幕府的貢品,與大阪與神戶的「下酒」形成對比,成為島津氏的代表貢品。泡盛使用泰國米為原料,並以「全麴釀造法」省略二次醪工序,因此也被視為現代燒酎「全麴釀造」的先驅。而黑麴菌產生的檸檬酸被證實適合高溫環境後,九州南部迅速從黃麴轉向黑麴,並衍生白麴變種。現今燒酎多用黑麴或白麴,清酒則以黃麴為主。
燒酎可粗分為單式蒸留燒酎(本格燒酎,或稱乙類燒酎)在原料發酵與原酒釀造過程上類似威士忌,但其以麴菌和酵母製成一次醪(酒母),再發酵原料(如地瓜、米)的二次醪工序則與清酒相同。相較之下,連續式蒸留燒酎(或稱甲類燒酎)透過反覆蒸餾穀類發酵液製成,過程中幾乎失去原料風味。
戰前燒酎多為家庭自用,明治30年代(約1897年)開始出現商用生產。1913年鹿兒島成立酒造組合,而在戰後因米糧短缺,地瓜燒酎開始崛起,並於1970年代首度超越米燒酎消費量,成為現今日本燒酎的主流原料。

大家熟知的濱田酒造 DAIYAME,歷史相當悠久。建議售價:$1,100
展露頭角|薩摩白波
在1970年代,鹿兒島芋燒酎「薩摩白波」以「6:4」的熱水稀釋比例為宣傳口號,透過廣播和電視廣告將這種飲法在全日本推廣。除了九州之外的消費者不再覺得燒酎味道過於強烈,進而開始嘗試。藉此,各燒酎酒造開始生產口感清爽的燒酎,新興「清爽型」燒酎開始崛起,在1983年,燒酎的出貨量首次超過威士忌,躍升為日本國內第三大酒類(僅次於啤酒與日本酒),從此讓清爽型的燒酎逐漸成為市場主流,並且開始被嘗試使用在調酒市場中。

清爽果香型的薩摩五代BEYOND GOD本格芋燒酎,建議售價 $1480
大放異彩|酎ハイ(Chu-Hai, Shochu Highball)與麥燒酎「iichiko」
1980年代,隨著日本連鎖居酒屋集團快速成長,以甲類燒酎添加碳酸(氣泡)與果汁的燒酎Highball(Chu-Hai)因價格低廉又容易飲用,受到年輕與女性族群的歡迎。於此同時,消費者也開始逐漸對燒酎感到好奇,擴大了另一項以原物料香氣為賣點的「本格燒酎」市場基礎,「米」、「麥」、「蕎麥」等具有獨特或是溫柔香氣的燒酎陸續出現在市場上。其中大分縣的麥燒酎「iichiko」因口感溫和加上針對30-40歲主力消費族群的廣告策略成功,成為這個時代的乙類燒酎代表品項。

麥燒酎成一大主流,濱田酒造 CHILL GREEN bitter&tropical 麥燒酎,建議售價 $990
溫故知新|黑霧島
2000年開始,以南九州為主要生產地區的地瓜燒酎(日文稱芋燒酎)酒造們開始有了另一波的變革。即是將傳統地瓜燒酎在原料、製程、包裝設計上大幅提升個性與質感,將這個國民酒精飲品區分出層次,也就是Premium Shochu的誕生。首先開始提出這個概念的就是宮崎縣霧島酒造的黑霧島。在2003年,日本燒酎消費量首次超越清酒,並在2007年達到100萬噸高峰。其中燒酎的「零糖與零普林值」更是讓許多傳統喝清酒的消費者開始轉向燒酎,以燒酎為主的酒吧也開始走出九州,出現在日本各大都會區。

時代的先驅:霧島酒造 Kirishima No. 8 霧島8號 芋燒酎,建議售價$990
市場變化與巨大酒造誕生|霧島、三和、OENON
2010年後,燒酎市場雖趨向成熟,但隨著日本年輕族群飲酒人口下滑,加上2019年起因疫情造成餐飲業與中小型酒造衰退,燒酎市場與競爭逐漸趨於少數幾家大酒造中,並呈現主導地位。以2020年營業額為例,霧島酒造以623.35億日圓居首位,三和酒類(iichiko)約429.63億居次,OENON以約393.57億排行第三。三家合計佔據燒酎市場近半營收。這些酒造不斷加強品牌線與多樣化產品組合,並在資本、行銷及通路上形成壁壘,使中小酒造在全國市場上生存壓力加大。

燒酎市場獨佔的問題相當嚴重,市占第一的霧島酒造營業額遠超其他品牌,虎斑霧島乃霧島酒造在干支虎年所出的限定品項。
燒酎的未來與下一步?
近年來,燒酎製作技術不斷演進。除了出現「減壓蒸餾」與「桶熟製程」外,還包括添加乳酸菌、控制酵素活性、改良型單缸蒸餾器等,使得燒酎的香氣和口感更加穩定和多變。這些技術使不同原料與麴菌(米、麥、地瓜等)之間互相搭配,發揮獨特的風味與特色。
而日本國稅廳自2006年起在部分地區在有附帶條件下開放新的釀造許可,允許小規模本格燒酎廠設立。這項政策轉變使得更多地方型中小酒造能進入市場,帶來了品種和風格的多樣性。另一方面,針對甲類燒酎的新設立則加以規範,間接促使大型酒類企業整併。整體而言,法律鬆綁和技術革新成為燒酎下一步前進的基礎。

因法律鬆綁,近年來逐漸有新興酒造進入市場。研釀株式會社 貓頭鷹 芋燒酎,建議售價 $1180
燒酎在台灣市場的狀況
台灣整體進口酒類雖從2002年的28%攀升至2022年的49%,但日本產酒類相較於啤酒與清酒,日本進口燒酎佔烈酒進口比例仍低於1%,其中主要幾個瓶頸點大致區分如下:
(1)40%高關稅門檻使得終端售價大幅上揚。
(2)25%酒精濃度處於品飲市場中的模糊地帶,相較於調酒與低酒精飲料,傳統燒酎對年輕世代仍屬高酒精類飲品,但對烈酒愛好族群又被認為不夠醇厚。因此燒酎必須以更多元的飲用方式來創造全新的客群。
(3)本土品牌的挑戰:面對高關稅,台灣製酒業者以本地農產原料,發展地方特色燒酎,成為日本進口燒酎強勁的競爭對手。
台灣燒酎市場正處於成長調整期,日本各式特色燒酎進口與本土化並行,面對同樣處於少子化與低飲酒趨勢,未來仍需生態圈業者們一起努力與推廣,以鞏固並擴大在台灣烈酒市場的地位。

從圖中可看到,截至2025年2月,台灣的進口酒類佔總比已超過半,其中燒酎只佔其冰山一角。 圖片來源:財政部國庫署
日文版原文
GW連休で鮫島吉廣先生の名著『焼酎の履歴書』を拝読し、また焼酎への認識や理解をまとめた。ご関心のある皆さまの参考になれば幸いです。
●「焼酎」の歴史|泡盛から始まる
焼酎は日本の伝統的蒸留酒であり、現存最古の日本産蒸留酒は15世紀の琉球王朝期に成立した「泡盛」とされています。江戸時代には、薩摩藩が幕府への献上品として泡盛を贈り、大阪や神戸の「下り酒」と対をなす島津氏の名物となりました。泡盛はタイ米を原料に「全麹(ぜんこうじ)仕込み」で二次醪を省く製法を採用しており、現代本格焼酎の「全麹仕込み」の先駆けともいえます。
高温多湿の南国環境下で安定生産を可能にしたのが、黒麹菌のクエン酸生成であると1918年に証明されて以降、九州南部では黄麹から黒麹、さらにその突然変異である白麹へと麹菌が移行しました。現在、焼酎には黒麹か白麹が、清酒には黄麹が主に用いられています。
焼酎は大きく単式蒸留焼酎(本格焼酎≒乙類焼酎)と連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)に分かれます。単式蒸留焼酎は原料を一次醪(酒母)→二次醪の手順で発酵させ、ウイスキー同様に原酒を蒸留しますが、一次・二次醪の工程は日本酒と同じく麹と酵母を用いる点が特徴です。
一方、連続式は穀類等のもろみを繰り返し蒸留し、原料風味をほぼ失わせることで大量生産を可能にします。
戦前は家庭消費が主体で、明治30年代(1897年頃)から商業生産が始まり、1913年に鹿児島で酒造組合連合会が設立されました。
戦後の米不足を契機に芋焼酎が急速に普及し、1970年代には芋焼酎が米焼酎の消費量を初めて上回り、今日の主力原料となりました。
●初のブレイク|薩摩白波
1970年代、鹿児島の芋焼酎「薩摩白波」はお湯割り比率「6:4」をキャッチフレーズで、ラジオやテレビCMを駆使して全国展開を図りました。
九州以外の消費者も“芋のクセ”を強く感じずに飲めるようになり、これを受けて各蔵元は口当たり爽やかな「ライトタイプ」の焼酎を続々と開発。1983年には焼酎の出荷量が初めてウイスキーを超え、ビール・日本酒に次ぐ国内第三の酒類へと躍進し、年配層だけでなく広く市場に浸透しました。
●新たな広がり|酎ハイと「いいちこ」
1980年代、居酒屋チェーンの拡大に伴い、甲類焼酎を炭酸や果汁で割った酎ハイ(シュワシュワ系飲料)が若年層・女性に大人気となりました。並行して「本格焼酎」市場も拡大し、米・麦・蕎麦といった原料由来の香りを活かす品項が増加。
大分県の麦焼酎「いいちこ」はマイルドな飲み口と30~40代を狙った広告戦略により、乙類焼酎の代表格として全国的ヒットを記録しました。
●伝統と革新|黒霧島
2000年代に入ると、南九州の芋焼酎蔵元は原料選定・製法・パッケージデザインを総合的にブラッシュアップし、「プレミアム焼酎」カテゴリーを切り拓きました。その先駆けが宮崎県の霧島酒造による「黒霧島」です。
2003年には焼酎消費量が清酒を超え、2007年には出荷量100万キロリットルのピークを迎えました。さらに“糖質ゼロ・プリン体ゼロ”をアピールすることで、従来清酒を好んでいた層も焼酎にシフト。焼酎専門バーも九州を飛び出し、全国主要都市で見られるようになりました。
●市場変化と大手蔵の台頭|霧島・三和・OENON
2010年代以降、若年層の飲酒人口減少や2020年以降の飲食店支援減少により、焼酎市場は成熟と縮小が同時進行。市場シェアは霧島酒造、三和酒類(iichiko)、OENONの3社が約半分を占める寡占状態となりました。2020年度の売上高はそれぞれ約623億円、430億円、394億円で、中小蔵の全国展開はますます厳しさを増しています。
●次なる一手|技術と規制緩和が拓く未来
近年、焼酎製造では減圧蒸留、樽熟成、乳酸菌添加、改良蒸留器など多様な技術が導入され、香味の安定化・多様化が進んでいます。また、2006年に国税庁が一部地域での小規模本格焼酎蔵の新規許可を開始したことで、地方の新興蔵元が参入し、多品種化・地域ブランド化が進行中です。一方、甲類焼酎の新設規制は依然厳しく、大手企業の統廃合を促しています。こうした技術革新と法制度の変化が、焼酎産業の次なる飛躍を支えるでしょう。
●台湾市場の動向
台湾の輸入酒市場に占める比率は2002年の28%から2022年に49%へ上昇したものの、日本産焼酎は烈酒輸入全体の1%未満にとどまります。主な課題は次の3点です。
1. 40%の高関税 により小売価格が大幅に上昇し、消費拡大の障害となっている。
2. 25度前後のアルコール度数は中途半端なところと受け取られ、若年層への訴求が難しい。
3. 本土ブランドの台頭:台湾産地の農産物を活用した地元焼酎が開発され、日本産焼酎の強力なライバルとなりつつある。
台湾市場は輸入品と本土品が並存する過渡期にあり、少子化・飲酒離れという共通課題を抱えながらも、協会や業界各社によるプロモーション強化、通路開拓、製品差別化を通じて更なる成長を目指しています。
責任編輯:潘昱嘉
核稿編輯:陳慧