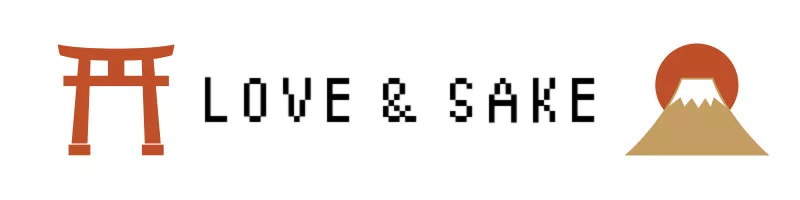前日在文章中曾提到今年日本全國新酒鑑評會結果中,兵庫縣與愛知縣整體表現衰退,可能有許多主客觀因素,例如天候與收成狀況、優質酒米的確保、縣內酒造規模差距大以及當地酒造組合是否能扮演一個強而有力的領導角色等,但這也僅僅是我的推測。
剛好今日又看到南部美人藏元久慈先生的一篇文章,讓我想到在文獻爬梳中,曾看到這麼一篇期刊論文,是星城大學松原教授於2022年在日本經營診斷學會中所發表「新冠疫情後的村米制度對農家與酒藏的課題」,於是就想把它整理一下,跟各位分享。文中若有錯誤或不足之處也請各方給予包涵與指正。
村米制度指的是日本酒米生產地的農家與酒蔵之間,所簽訂的契作合作機制。通常一簽就維持數十年,而非一般按年或短期議價的買賣關係。對農家而言,有了保證 收購的訂單,能安心耕作並強化品質管理。對酒蔵而言,則可確保原料供應與價格,不必擔心市場波動。另外,藉由村米制度,農家與酒藏之間還能互換產量預估、品質動向等資訊,有助於雙方提高產量與品質。而當遇到疫情、天災或市場急速轉變時,村米制度也能減少因全縣或全國減產而造成的供應中斷風險。

圖片來源:管爺提供
新冠疫情期間對村米制度造成的影響
松原教授以兵庫縣三木市吉川町村米農家代表與酒藏,自2020年6月至2022年3月分四期進行訪談,蒐集農家、農會、JA與酒藏等不同立場的動態與意識變化。發現有以下變化:
-
村米制度因JA調配介入受到影響:原先可互創雙贏的村米契作制度因在疫情期間受JA兵庫的介入調配影響,原本酒藏可優先指定村米的機制遭弱化。
-
農家受疫情影響:疫情初期曾自發性以「買酒支援」行動購入酒藏酒品,但疫情擴大導致契作減量時,農家則束手無策,改向JA求援。
-
酒藏受疫情影響:酒藏面對2020年出口停擺及國內減產,僅能執行部分契約並分批收取;並接受JA調配機制。雖願意保留長期契約,但考慮未來改為短期協商。
-
長期趨勢:2021年度吉川町減產率約19%,雖低於全兵庫約25%與其他區域約35%;但疫情之後村米合約增產量僅微幅恢復約1.7%增長,顯示村米制度過去優勢已難恢復。
以本篇文章中的兵庫縣三木市吉川町為例,在2000年至2022年間,契約量由82,165袋減少至51,489袋,減幅約37%,其中2021年度受疫情影響尤其嚴重。另一方面,國稅廳「酒白皮書」顯示,同期餐飲業酒類消費大減52.7%及49.2%。在產能與需求雙重受挫的情況下,傳統村米制度的韌性受到極大挑戰。

圖片來源:管爺提供

菊姬 山廢 無濾過 純米生原酒 建議售價:1960
新冠疫情後面臨到的酒米生產與食用米供應問題
村米制度雖在疫情期間受到JA強勢介入而遭到弱化,但也帶出了日本農產上的結構性問題
1.JA統一調配下,酒藏無法自由指定產地與優先購買配額,讓透過村米制度所建立起的農家與酒藏之間的人際與生產資訊交換網絡隨之弱化。
2.研究中發現約65%的受訪農家年齡超過60歲,僅有不到15%為35歲以下。農村人力短缺與以及對耕作技術的續承問題,加速了生產意願與品質的下降。
3.JA在金融、技術推廣與市場行銷上雖具資源,但在在地化管理與對青農吸引力方面相對薄弱,未能提供足夠誘因留住下一代農民。
4.隨著清酒市場多樣化,市場M型化明顯,原料用量大的酒藏改為與大型農業公司以其他便宜米種替代,讓生產高品質酒米的米農耕作意願低落,供給變少,價格上揚,讓倚賴山田錦為主的酒造面臨經營壓力。

圖片來源:管爺提供

圖片來源:管爺提供

吉川釀造 雨降 Ringosan 77 建議售價:$1,500
我對JA未來或許可以扮演的角色的建議
-
強化在地直接協商:重新建構農家與酒藏間的直接溝通管道,由JA保留30–40%核心契約配額,由讓農家可自主分配,並建立與酒藏的定期座談會機制,確保雙方需求即時反饋。
-
制度化資訊平台:構建公開透明的產量、價格與需求資訊平台,兼具記錄、追溯與即時通報功能,替代過度倚賴原先村米制度下的人際傳播模式。
-
農業生產法人與青年扶植:透過稅收減免、低息貸款及技術派遣等政策,鼓勵青年與外地專業人員進入村米區,並推動成立農業生產法人,集中閒置農地,提高經營規模效益。
參考資料:
1.新型コロナウイルス禍により見えてきた村米制度の農家と酒蔵の課題
, 松原茂仁, 日本經營診斷學會論集 22, 96–101(2022)
1.新型コロナウイルス禍により見えてきた村米制度の農家と酒蔵の課題
, 松原茂仁, 日本經營診斷學會論集 22, 96–101(2022)
2.清酒の製造状況等について令和5酒造年度分, 国税庁課税部鑑定企画官, 2025.02
延伸閱讀
日文版原文
◎日本の村米制度が酒造業に及ぼす影響について
●前書き
先日、今年全国新酒鑑評会の結果に関する拙筆に、兵庫県と愛知県の成績について、主・客観的要因があると述べました。例えば、天候条件や収穫状況(登熟期不作)、良質な酒米の確保、県内蔵元の規模差、地域の酒造組合の行動などが挙げられますが、これらはあくまで僕の推測です。
本日南部美人蔵元の久慈氏の記事を拝見し、または文献整理の過程で星城大学の松原教授が2022年に日本経営診断学会で発表された論文『新型コロナ禍における村米制度の農家と酒蔵の課題』を思い出しましたので、整理して共有いたします。本文に誤りや不備がございましたら、何卒ご容赦のうえ、ご指摘賜りますようお願い申し上げます。
●『村米制度』とは
村米制度とは、日本酒用酒米の産地農家と蔵元との間で結ばれる契約栽培協力の仕組みです。通常、契約は数十年単位で維持され、年間契約や短期的な交渉による売買関係とは異なります。農家にとっては、買い取り保証があることで安心して栽培に専念し、品質管理を強化できます。蔵元にとっては、原料の供給量と価格を安定的に確保でき、市場の変動を気にする必要がありません。
また、村米制度を通じて農家と蔵元は収量の見通しや品質動向などの情報交換を行い、双方の収量および品質向上に寄与します。さらに、パンデミックや天災、市場の急激な変化が発生した際には、村米制度が県全体や全国規模の減産による供給途絶リスクを軽減します。
●新型コロナ禍における村米制度への影響
松原教授は兵庫県三木市吉川町の村米農家代表と蔵元に対し、2020年6月から2022年3月まで4期にわたってインタビューを行い、農家、農協(JA)、および蔵元の意識と動向の変化を収集しました。その結果、以下の変化が明らかになりました。
-
JAの配分介入による村米制度への影響:従来、双方にとって有益であった村米契約栽培は、コロナにJA兵庫の配分介入を受け、蔵元が村米を優先指定する仕組みが弱体化した。
-
農家の動向:コロナ初期には『買い支援』として自発的に蔵元製品を購入したものの、感染拡大に伴う契約減産時には農家は対応策を欠き、JAへ支援を求めた。
-
蔵元の動向:2020年の輸出停止と国内需要減少を受け、契約の一部履行のみを分割して行い、JAの配分メカニズムを受け入れた。長期契約維持の意向は示したものの、将来的には短期協議へ移行する可能性を検討。
-
長期的傾向:2021年度の吉川町における減産率は約19%で、兵庫県全体の25%および他地域の35%より低いが、コロナ禍後の村米契約量回復は約1.7%の微増にとどまり、従来の優位性が回復困難であることを示唆した。
この論文では、例として兵庫県三木市吉川町において、2000年から2022年にかけて契約量が82,165俵から51,489俵へ約37%減少し、特に2021年度のコロナの影響が顕著であったと報告しています。一方、国税庁の『酒のしおり』によれば、同期間の飲食業界における酒類消費は前年度比で52.7%および49.2%減少しました。生産能力と需要の両面が打撃を受けた状況下で、伝統的な村米制度の優位性が減りました。
●コロナ禍に直面する酒米生産と食用米供給の課題
村米制度はコロナ時期にJAの介入で上記のように弱体化しましたが、同時に日本の農業構造上の課題も浮き彫りにしました。
-
JAによる一元的配分の下で、蔵元は産地指定と優先購買権を失い、村米制度で構築された情報交換網が弱まった。
-
研究では、約65%の農家が60歳以上、35歳以下は15%未満であり、後継者不足と技術継承問題が生産意欲と品質低下を加速させている。
-
JAは金融支援や技術普及、マーケティング資源を有するが、地域管理や若手農業者誘致には十分な魅力を提供できていない。
-
清酒市場の多様化とM字型市場構造の進行に伴い、大規模蔵元は他産地や安価な米種と契約する動きが増え、高品質酒米生産農家の意欲低下と供給減少、価格上昇を招き、山田錦主体の酒蔵が経営圧力に直面している。
●JAが果たし得る今後の役割の私見
-
地域直接協議の強化:農家と蔵元間の直接コミュニケーションチャネルを再構築し、JAは30~40%の契約枠を保持して農家の自主配分を認め、定期的な座談会を設け即時の意見交換を実現。
-
情報共有の制度化:生産量、価格、需要情報を公開するプラットフォームを構築し、記録・追跡・リアルタイム通報機能を備え、従来の人脈依存型情報伝達を補完。
-
農業生産法人化と若手支援:税制優遇、低利融資、技術派遣などの政策支援で若手・外部専門人材の参入を促し、農業生産法人を設立、生産規模を拡大。
-
差別化ブランド構築:村米をコアブランドとし、地理的表示(GI)制度や地域観光と連携し、蔵元訪問体験や文化イベントを通じて消費者参加を促進し、付加価値と価格プレミアムを向上。
●参考文献
-
松原茂仁, “新型コロナ禍により見えてきた村米制度の農家と酒蔵の課題,” 日本経営診断学会論集, Vol.22, pp.96–101, 2022.
-
国税庁課税部鑑定企画官, “『清酒の製造状況等について』令和5酒造年度分,” 2025年2月.
責任編輯:潘昱嘉
核稿編輯:陳慧